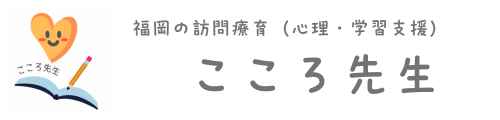ある授業の一コマ~書き直しさせる?させない?
こんばんは!福岡で臨床心理士による心理・学習支援を行っている「こころ先生」です♪
今日は授業で、生徒さんと「しりとりプリント」に交互に単語を書いていく課題をしました!
文字数の指定があるので、普通の「しりとり」よりも難易度が上がります。
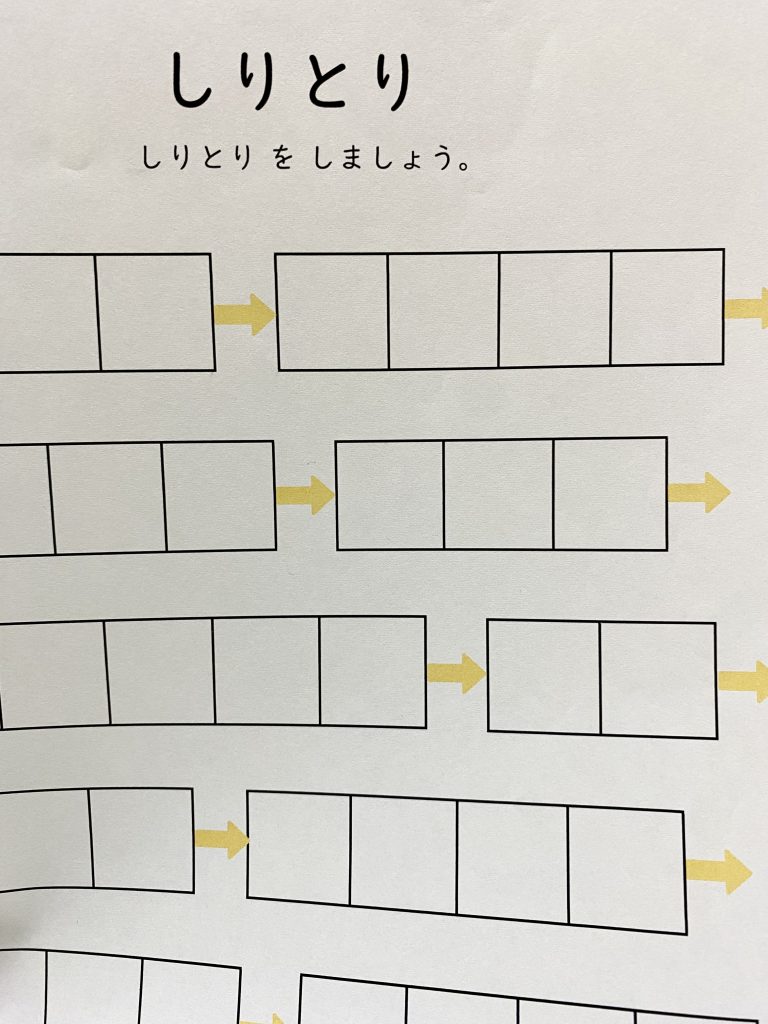
↑こんなプリント
2~3往復したところで「みかん」と書き込んだ生徒さん。
想定よりも早く「しりとり」のラリーが終了してしまいました …!
突然ですが、みなさんはこのあとどう対応しますか?
書き直しをさせる?「ん」がつかない他の答えのヒントをあげる?
様々な対応があると思います。
一般的には、プリントに書いた文字を書き直してもらうという対応が多いのではないでしょうか。
私も、自然な流れで消しゴムを手に取りました。
しかし、ここでふとこんなことが頭によぎりました。
国語に苦手意識が強い生徒さん。
楽しそうに始めたしりとり。
しばらく考えてやっと思いついた言葉。
一生懸命書いた文字。
ここで書き直しをさせることが、本当にその生徒さんのためになるのか。
せっかくのやる気を削がないか。国語がますます嫌いにならないか。書き直してほしいのは私の都合ではないのか。
ここは「みかん」を思いついてプリントに書いた生徒さんの気持ちを汲み取ってあげたい。
「ん」で終わってしまったけれど、また次のマスから新たなお題で「しりとり」を始めたらいい。
「ん」がついてしまった、間違えてしまった、書き直しだ、という失敗経験にするのか。
それとも「ん」がついたけれど、「み」から始まる3文字の言葉を思いついて書けたという成功体験にするのか。
この生徒さんにとって今必要なのはどんな対応だろうか。
もしかしたら、「甘やかしてはいけない」「ルールは守るように教えるべきだ」「間違いをはっきり指摘しないのは子どものためにならない」という意見もあるかもしれません。
ですが、これまで学習(もしかしたら学習以外のことでも…)で何度も何度も失敗経験を積んできて、自信をなくしてしまっているお子さんの場合は、それが必ずしも正しいとは言えないのではないかと私は考えています。
それに、学校の先生や親という立場だったら、「ルールは守りましょう」「間違ったことは正しましょう」という指導・しつけは必要だと思います。
しかし、学校の先生でもない、親でもない、私の立場だからこそ、ちょっと違った対応ができるのではないかとも思っています。
ルールをしっかり教える立場の大人もいれば、ゆるーい大人がいてもいいのではないでしょうか。
…だめかな?いいよね!笑
そんなことを考えた授業の一コマでした。
こころ先生は、学習の遅れ、特別支援、不登校など、より丁寧な個別サポートが必要なお子さまのための家庭教師です。
主に福岡県春日市・那珂川市周辺で訪問による心理・学習支援を行っています。
オンライン授業も行っているので、その他の地域にお住まいの方にも対応可能です。
2025年度、新規生徒さん募集中!対応できる枠に限りがあります。お申し込みはお早めに♪