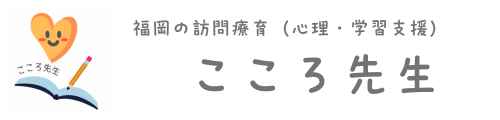自分で学んでいける子になるには?ちょうどいい課題設定の重要性
福岡県(春日市、那珂川市、大野城市周辺&オンラインも対応!)で、臨床心理士による心理・学習支援を行っている「こころ先生」です♪
8月に入りました!毎日暑いですね~!みなさん、夏バテしてないでしょうか?
福岡は連日40度近い暑さが続いております…(汗)
こうなってくると、我が家の子どもたちを外遊びに連れていくのはなかなか難しく、ここ最近は家の中で遊ぶことが多かったのですが、
今日は、私も子どもたちも早起きしたので、子どもたちを連れて朝の公園(遊具がたくさんある大きめの公園!)へ行ってきました!
子どもたちと一緒にこの公園にきたのは久しぶり!
(すでに30度近い気温で、ぎり遊べるかな?という感じでしたが…)
短時間ではありましたが身体を思いっきり動かして遊ぶことができました。
久しぶりに公園に来ると、以前は子どもたちにとって登るのが難しかった遊具も、自分の力で登れるようになっていて、
「できたよ!」と嬉しそうな表情で報告してくれる姿をみると、成長したなぁと感じます。
子どもたちも、以前はできなかったことができるようになったことを実感したようで、自信になっているようでした。
そして、また別の難しそうな遊具に「これやってみる!」と挑戦していきます。
そんな姿を見ていて、ふとこんなことを思いました。
それは【公園で遊ぶことって、学習の過程と似ているな】ということ。
まだ少し難しいかな?という遊具に憧れて「これやってみたい!」と挑戦する姿。
「あと一段登ってみよう」「まだいけるかな?」「よし!もう一段登ってみよう」
小さく小さく挑戦して、登ることができると
「見て!登れたよ!」と嬉しそうな表情を見せてくれます。
この過程が、学習の過程に似ているなと思って。
自分の身体能力よりはるかに上回る遊具には見向きもしなかったり、無理やり挑戦させると怖がって、「あの遊具はこわい」と避けてしまいますが、
成長とともに身体能力が上がってくると、「一段だけなら登れるかも!」「途中までなら登れるかも!」と挑戦しようとします。
はじめは大人が下から支えてあげたり、少しだけ手伝ってあげたりしながら自信をつけ、
それから少しずつ支えていた手を放し、途中まで自分の力で登れると自信になり、最後は自分の力で登れるようになる。
学習も同じ。
【遊具→学習課題】に置き換えてみると、
自分の今の理解度よりも、はるかに難しい課題(遊具)をたくさん出されると、課題(遊具)を見る気にもならないし、やる気にもなれないですが、
自分の今の理解度よりほんの少し難しい、ちょっと頑張ればできそうな課題(遊具)を出すと、「少しやってみようかな」「できるかもしれない」と思って挑戦してくれます。
※この「少し頑張ればできる」「サポートがあればできる」領域のことを心理学では【発達の最近接領域】と言います。
少しできると、「自分にもできた!」「もしかしたら次もできるかもしれない」「もう一度挑戦してみよう!」
良い循環が生まれて、自信がついていきます。
この良い循環が生まれると、自分の力でどんどん学んでいきます。
できるようになるのが楽しいし、自分の成長を感じられるので、自らすすんで学んでいけるようになります。
なので、学習に使用する課題のレベルを適切に見極めることはとっても大事。
こころ先生は、一人一人の今にちょうどよい課題を設定することに、とことんこだわっています!
丁寧なアセスメントでお子さんの今の理解の段階を知ること、そしてそこから小さいステップを組んで成功体験を積んでいくこと。
これができる点は、臨床心理士が学習を教える上での強みだと思います♪
こころ先生は、学習の遅れ、特別支援、不登校など、より丁寧な個別サポートが必要なお子さまのための家庭教師です。
一人一人のペースに合わせた心理・学習支援を行っています。
主に福岡県春日市・那珂川市周辺で訪問による心理・学習支援を行っています。
オンライン授業も行っているので、その他の地域にお住まいの方にも対応可能です。
もし、「学校の宿題や市販の教材は見向きもしてくれない」「塾や家庭教師でも全然やる気になれず学習が進まない」などのお悩みがありましたら、一度個別相談でお話聞かせてください。
やる気がないのは、もしかしたら今のお子さんに合った課題が設定できていないからかも!?
お子さんの今にちょうどよい課題を見極め、無理なく楽しく学べる方法をこころ先生と一緒に考えていきましょう♪